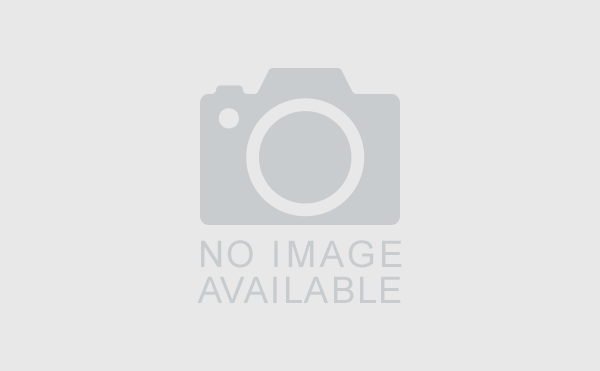18時間「主食」を食べない→「オートファジー」と「サーチュイン遺伝子」活性化
18時間「主食」を食べない→「オートファジー」
18時間「主食」を食べないことで「オートファジー」を起こす。
「オートファジー」とは?
オートファジーは、細胞内の不要な物質を分解・リサイクルする生命維持に不可欠なシステムです。この仕組みは、細胞の健康を保ち、健康長寿や老化防止、免疫力向上に寄与します。具体的には、細胞成分の入れ替え、有害物質の排除、飢餓時の栄養確保といった役割を担っています。
年齢とともに低下するオートファジー機能は、適度な運動やバランスの取れた食事、十分な睡眠といった生活習慣の改善、そしてウロリチンAやレスベラトロールなどの栄養成分の摂取によって活性化が期待できます。
日本はオートファジー研究をリードしており、ノーベル賞受賞者も輩出しています。UHA味覚糖は大阪大学と共同で、ウロリチンAとレスベラトロールの組み合わせによるオートファジー活性化効果などを研究し、健康増進に役立つ食品開発を進めています。今後の研究により、ヒトへの応用や更なる健康長寿への貢献が期待されています。
(出典:【公式】オートファジーとは何か?お菓子のUHA味覚糖が世界一わかりやすく解説- UHAヘルスケア研究所 | UHA味覚糖 https://www.uha-mikakuto.co.jp/healthcare/autophagy/index.html)
18時間「主食」を食べない→「サーチュイン遺伝子」活性化
18時間「主食」を食べないことで「サーチュイン遺伝子」を活性化する。
「サーチュイン遺伝子」とは?
サーチュイン遺伝子は、「長寿遺伝子」とも呼ばれ、老化や寿命の制御に重要な役割を果たします。この遺伝子の活性化は、動物実験で老化制御に繋がる効果が報告されており、ヒトを対象とした臨床試験も進められています。
研究のきっかけは、2000年に発表された酵母のサーチュイン遺伝子(Sir2)に関する研究で、この遺伝子の機能を強化すると酵母の寿命が延びることが明らかになりました。現在、哺乳類にはSIRT1からSIRT7までの7種類があり、特にSIRT1は血糖値の調整、糖や脂肪の代謝促進、神経細胞の保護など、老化や寿命のコントロールに深く関与しているとされています。
サーチュイン遺伝子の活性化には、NAD(ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド)が鍵となります。NADは細胞のエネルギー産出に不可欠な補酵素で、サーチュインを活性化させる役割を持ちます。加齢とともにNAD量は減少しますが、運動やカロリー制限、NMN(ニコチンアミドモノヌクレオチド)の摂取などでNADを増やすことにより、サーチュインを活性化させ、老化を遅らせる効果が期待されています。
(出典:サーチュイン遺伝子|Beyond Health|ビヨンドヘルス https://project.nikkeibp.co.jp/behealth/atcl/keyword/19/00113/)